
<今年、語り伝えたいこと>
「こちらの信仰とか不信仰とか、一切こちらの考えとか働きとかによらない、それとは全然別なこと、こっちが知ってても知ってなくても・信じても信じなくても、神様はちゃんと共にいらっしゃるということ、神様に結びつけられていない・限界づけられていない人間なんてものはいない」(滝沢克己『聖書を読む マタイ福音書講解』第2巻、創言社、61頁)
神様の神様の方から、すべての人と無条件に共にいて下さり、それゆえにすべての人はすでに救われております。ご安心ください。
救いは罪から入るものではありません。救いはすでに赦されているこの大前提の事実においてすでに成立しております。自分は罪人である、と考えすぎて自分を傷つけないようにしましょう。
今年は滝沢克己が見出した、この「インマヌエルの原事実」を、語り続けます。‶人の生の大前提として在るこの「救い」が見失われていたことは、救いを旨とするキリスト教が、自らの内と外で、排除・断罪し争い合うようになった大きな要因の一つであろう、と私は考えております。″
この大事な福音理解を、すべての方々と共有したいと思います。
* * *
『十字架の祈り』は、私の個人伝道雑誌です。今年はこの大切なインマヌエルの福音を、この雑誌でも語り続けます。
『十字架の祈り』毎月1回発行。頒布価格(送料含)一部300円 年間購読料3,600円。
〔申込み〕郵便局備え付けの振替用紙に内容を明記の上、下記振替口座にご入金ください。
00180‐3‐764366 加入者名: 十字架の祈り社
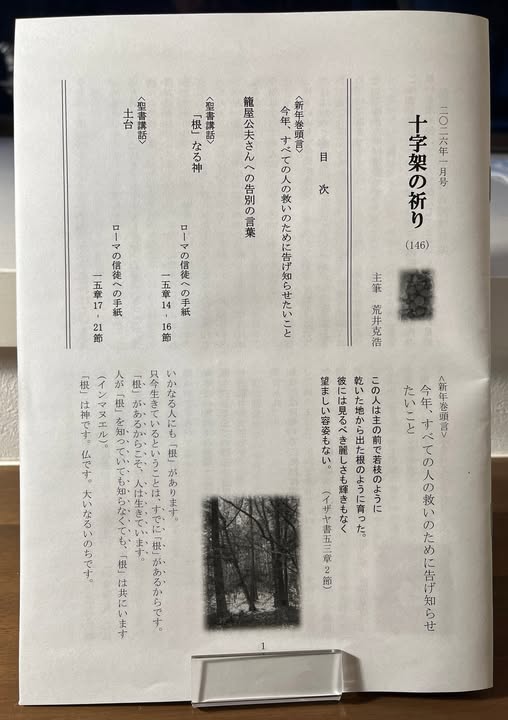
2026年1月
無教会 独立伝道者
荒井克浩
<礼拝>
現在、今井館で礼拝を行っています。(ご事情で会場にお越しになることが難しい方々はZOOMでのご参加)。
礼拝日時:毎週日曜日 10時~12時
会場:今井館 第2第3集会室 東京都文京区本駒込6-11-15
※ご参加に際してのお願い:今井館の入り口はセキュリテイがかかっていますのでそのままでは入れません。礼拝開始は10時からですが、9時30分以降に、入り口脇にあるインターフォンの数字ボタン「203」を押してから「呼び出し」を押してください。中から応答いたします。参加者と認められた場合は、中から入り口をお開けします。
■滝沢克己著・滝谷美佐保編『中学生の孫への手紙——人生の難問に答えて』(ヨベル)出版のお知らせ。2025年12月出版(すでに出版されております)。
税込価格:1320円(本体価格: 1,200円)
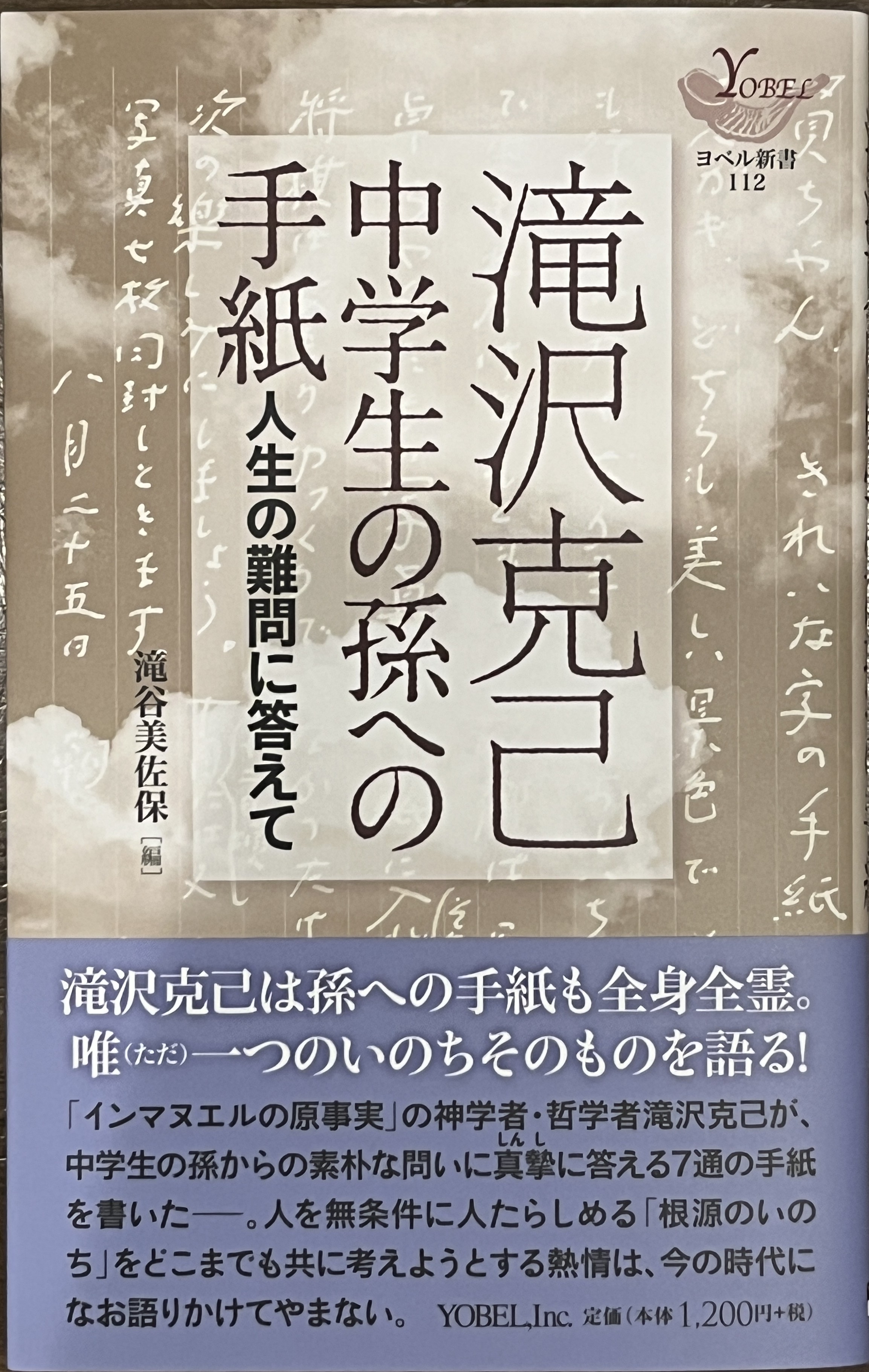
召天される2か月前までの2年間、滝沢克己が人生の難問を持つ中学生のお孫さんへ、7通の手紙を送りました。どれも可愛いお孫さんへの愛がこめられつつも、ゆるぎない「いのち」を指し示す、大事な内容です。
最晩年の手紙であり、また愛するお孫さんに宛てたものであり、嘘偽りのない滝沢克己の信仰が結実して現れております。手紙であり、そんなに頁数もありませんので、読みやすいと思います。
私の「解説にかえて——滝沢克己先生との出会い」という文章も収められております。この文章は、今に至る私の信仰の、小さな履歴でもあります。
クリスマスプレゼントにもいかがでしょうか。(荒井克浩)
■荒井克浩著『無教会の変革――贖罪信仰から信仰義認へ、信仰義認から義認信仰へ』(教文館)出版のお知らせ。出版日:2024年3月25日 税込価格:1980円(本体価格: 1,800円)
【教文館新刊案内より】
「信仰は条件闘争ではない。
私は全国のキリスト者の声を聞くうちに、贖罪信仰がいかに信者を追いつめてきたかを知った。 そんな中、荒井克浩先生の信仰の変化は暗闇に差す光だった。信じれば救われるのではなく、すでに救われている。それが信仰の出発点なのだ。」最相葉 月氏推薦!
「荒井氏は謙虚にも、自らがその中へと置かれている『無教会』の『変革』に焦点を絞った著書名を選択したが、言うまでもなくこの問題の射程は、より広く、より遠くにまで、即ちキリスト教の『正統信仰』そのものの『変革』にまで及んでいる。」青野太潮氏推薦!
一人の無教会伝道者として、内村の信じた贖罪信仰をいま、問い直す──
無力な「十字架につけられたままのキリスト」に集中することから生まれた、新しい信仰の展望を描き出す書
―――――――――――――――――――――――――――――
【目次】
<推薦の言葉>それは無教会だけの問題ではない(青野太潮)
まえがき
第一章 はじめに総論として
第二章 贖罪信仰から信仰義認へ
第三章 無教会の信仰における断絶と継承
第四章 無教会への問題提起
第五章 そのままでよい──神によるありのままの受容
第六章 全ての人への神の無条件の愛
第七章 「十字架につけられたままのキリスト」──復活理解
第八章 捨てられた神と共に
第九章 信仰義認から義認信仰へ
第一〇章 「贖罪信仰」の底を割ってその先へ進む
参考文献
あとがき
―――――――――――――――――――――――――――――
■最相葉月『証しー日本のキリスト者』発刊のお知らせ
ノンフィクションライター最相葉月さんの『証しー日本のキリスト者』がKADOKAWAから出版されました(2023年1月13日発売開始)。教派を超えた135人ものキリスト者の証しが掲載されている1000ページ以上に及ぶ大著です。私たちの集会にも、4年ほど前から取材に来て下さり、荒井克浩や集会の方々の証しが掲載されています。また「あとがき」では、荒井の信仰に関することを書いてくださっています。神学書とは違い、混迷極まるこの時代における様々な信仰の証しを、生きた言葉として、難しくなく読める本です。3,180円(税別)
★伝道雑誌『十字架の祈り』78号から105号まで(主筆・荒井克浩〔駒込キリスト聖書集会主宰〕)をご購読ください。





